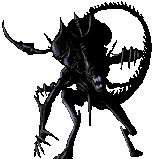 from3.5次元to浄土
from3.5次元to浄土俺と音盤の対峙一部始終。(text=色即zk)
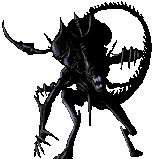 from3.5次元to浄土
from3.5次元to浄土vol.7
| ニセ予言者ども/じゃがたら | ||
 |
糞を食らわねばならなかったのはアケミが潔癖過ぎたからだろうと俺は思う。世界そのものが汚物まみれである以上、自らも汚物まみれになってみせることでしか美や清廉や貞潔というものは守り通すことが出来ぬとよくよく肝に命じておくべきだ。しかも「〜教」や「神」と癒着やら結合した救済がまやかしに過ぎぬことなど当然過ぎるほど当然なので救われる訳ゃねえよど阿呆。「ども」と言わざるを得ぬほどにニセ予言者(メディア操作その他)が次から次へと後を絶たぬのはアケミが死んで早10年経とうという今もつくづく変わらねえじゃねえか。って変わる訳もないが。でもやるんだよ。「周りは宇宙的レベルで少しずつ変わっていく」(『都市生活者の夜』)し「やりたいことがいっぱい残っている」(『みちくさ』)と本気で思えるなら、溢れ返るリズムの奔流の中にのみ「救済」は今も確かに在り続けている。シマヘビやニワトリを食いちぎり服を一枚ずつ脱ぎながら歌い額をカミソリで切り紙コップに放尿しそれを飲み吹き出しまた頭からかぶり驚きで動けない女の客に抱きつき床を転げ回り自らの肛門にイチジク浣腸をしヤワい大便を垂れ流しながらイスを振り回し客を追いかけ割れたビール瓶の破片で全身を切りまくり救急車で病院に担ぎ込まれようという奴は今の日本に一体何人いるか?誰もやらなきゃ自分がやりゃいいというそれだけの話だろ。やれよ。 | |
| can box | ||
 |
|
|
| encontro com a velha guarda/compilation | ||
 |
(オーマガトキ発なので今ならまだ新星堂で見つかるかも)自らにとって特別だった「誰か」や「何か」を完全に失うこと。例えば、重度の失恋や身内の葬式や挫折感や敗北などなど。そういった「本当に痛すぎる」状況をまぬがれ得ぬこともまた人の業/限界ではある。しかし、だからこそ「敢えてでも」笑う。「だからこそ」歌ってしまうという奴もいる。音楽をはじめ感動の本質とはいつもこの「敢えて」の中にこそあると俺は信じて疑わない、今や。encontro com a velha guarda (邦題=「すばらしきサンバの仲間たち」)はエルナーニ・ジ・アルヴァレンガの“最低賃金”をはじめ「切なすぎる想い」のオン・パレードである。エスコーラと呼ばれるサンバ共同体によるコーラスがそういった「痛み」や「切なさ」に思い思いの共感や励ましのエールを投げかけ、唱声を重ね合わすときに不意に感動は爆発する。あからさまな程、大らかだったり正直すぎる唱声の数々は聴く者の心にわだかまり続けてきたあらゆる「想い」を洗い流す。「敢えて」歌うことにこそ人の生きる訳があると訴えかける。決して悪びれてはいけない、とも。永遠に色褪せぬ究極の名盤。 | |
| 2000年のチャチャ/la! neu? | ||
 |
ダメな野即のままあり続けること、自らの「どうしようもなさ」を肯定し続けること、そしてそれらを実践しつつも「生き続ける」ことによってこそ到達・達成される境地は必ず存在する。俺や多くのご同輩にとって「あちら側の世界」とはまさにそのような意味において絶対的、普遍的なものだ。またそれは「いつか俺の正しさが証明される」と一人こぼさざるを得ない夜に見る「圧倒的な光」が降りそそぐ夢の具現化に他ならない。祈る気持ちの高密度化は今も密かに行われ続けている。クラウス・ディンガー=ラ!ノイ?の強靭な意志力を見よ。永久に続くハンマー・ビートこそ無垢な生命の胎動である。2枚組 100分を超える全1曲は糞やドラッグや馬鹿やマヌケやヘドや汚物にまみれた魂の浄化そのものである。来日ライヴの記録でもある本作にはステージ上に「光が降り立つ」様子が何度も鮮明にとらえられているし、ひたすらにループし続ける“cha cha 2000!!”のフレーズ(掛け声)は俺のどうしようもない日常を生き続ける力を与え鼓舞するものでさえある。ラ!ノイ?を「狂っている」とかぬかす奴らこそ余程アマいと知れ。「どうしようもなさ」にこそ神は宿る。 | |
| golden classics edition/the soul generation | ||
 |
郷愁かねえ。恋愛の「初期」に戻りたいと願う気持ちは、つねに俺の中に甘い記憶やつらさの集積として決して吐き出されぬまま確かに確かに燻り続けてきた。俺はそういった自分の気持ちを「無いこと」にさえしながら怠惰に毎日をただやり過ごしてきたに過ぎない。決して弱音を吐くまいと自分に言い聞かせることと、自分自身の「甘い想い」に対して不誠実な態度をとってしまうことの境界線は俺にとって曖昧なまま今もあり続けるが、俺がかつて選択をひとつ「間違えた」ということは今やはっきりと俺自身が分かってもいる。て、ため息。soul generation は決して有名であったり、トップ・グループとして扱われることの無い一見、地味なコーラス・グループではあるが、冬の澄みきった夜空やそこに輝く星々を思わせるコーラス×楽曲の数々は俺にとって絶対に「特別」である。若く未熟かもしれないが、ひたむきな想い、願いの美しさこそ真に貴いということを精一杯に表現しきっていて本当に本当に見事です。俺は今日、名曲“sailing”を聴いていたら涙が止まらなかった。いわゆるノーザン・ソウルの枠に収まりきらない実はかなり大胆なアプローチも多いが、あくまでも後味は爽快でもある。今もこのアルバムは俺の心の一番「甘い場所」に突き刺さり続けているし、俺の心からそれらが消えてしまうことはこれからも絶対に絶対にあり得ない。俺がこのアルバムを再びまともな気分で聴き返そうとする日もおそらくは一生来ないが…。「決して時間は戻せない」という当り前のことが本当に身に染みて分かる時、「新しい何か」は絶対に始まっているのだ。 |
⇒to vol.6 or ⇒back vol.8